物事や対人関係において対象や相手を「見極める」にはどう見れば良いのか。
ただ黙って眺めていてもそれは「見た」ことにならず、見極めるには至らない。
どんな方法で「見極める」に至るのか疑問に感じたことはないだろうか。
「見る」には漢字の違いや概念においてたくさんの種類がある。
そのうち「見極める」ために特に大切な要素3段階について紹介する。
1、「注視」は主に1方向から見続け、対象の動向・変化を見逃さない。
2,「視点を変えて見る」は1方向から見るのではなく自分自ら視点を変えながら見る。
3、「相手の立場から見る」は相手が自分や他の物事をどんな風に見ているかを想像して見る。
この概念を知っているだけで視野が広がると思うのでぜひ読んでみてほしい。
第一段階「注視」
一般的に「見る」と言えばこの「注視」を真っ先に思い浮かべるはず。
対象を一点の方向から注意深く確認し続けて認識し、
時間によって生じる変化や既知のものとの違和感を見つけて理解を深める見方だ。

この注視では、偏見や先入観を捨て素直に自分がどう思ったかを感じることが重要。
自分が思ったことを素直に受け止めることで疑問や興味が湧く。
次の段階に移る前に興味を自分の中で整理し、次にどこを見たいかを決める。
しかし視点を途中で変えてしまうと、自分が最初に感じた第一印象から離れてしまう。
視点を別の方向にしたせいで見ていた一面の変化の瞬間に気づけないということもある。
自分の中から沸き起こる感動と興味がひとまず落ち着いくまで見続けるのが良い。
落ち着いたら既知のものとの違和感やこれから先の変化の予測など探求心が芽生える。
何も湧き起こらないときは、第二段階へ進もう。
重要なポイントは、
見ているうちに理解が深まった結果、さらに新たな興味が連鎖して生まれること。
つまり見続けているうちに自らが変化していく。
この「感動」を大切にし、得たい情報を自分の中で整理しよう。
第二段階「視点を変えて見る」
「視点を変えて見る」は「注視」の状態から、自分や対象物を動かし別の面から見る方法。
物理的に自分や対象を動かすことは勿論だが、想像上でも視点を動かすことができる。
現在の境遇ではない別の境遇から対象を見るという視点。
違う場所や時間軸での視点。
推したり突いたり、刺激などの変化を与えた場合の視点。

「注視」を十分に行うことによって発生した感動や興味・疑問を
この第二段階「視点を変えて見る」で探求していく。
ここで「注視」が十分でないと探求心が湧かず、視点を変えても自分の得たい情報が分からない。
得たい情報が分かっていてもどこの視点で見ればいいのか分からず迷子になってしまう。
もし、第一段階で興味や感動が生まれなかった場合には、この段階で感動を感じるケースもある。
或いは探求した結果さらに新しい感動が生まれ、興味や疑問が再度発生することも多々ある。
重要なポイントは、
様々な視点から対象を見直すことで更なる新しい感動を得ること。
そしてまた第一段階に戻り「注視」を行う。
第一段階と第二段階を何度も経ることで結果的に膨大な情報を得ることができるだろう。
次段階ではこの膨大な情報を活用する。
第三段階「相手の立場から見る」
最終段階の「相手の立場から見る」だが、これが最も難易度が高く誤差や錯覚が生じやすい。
なぜなら相手の気持ちや考え、境遇は想像することしかできない。
幽体離脱して相手を乗っ取ったり、相手自身になったりすることができないからだ。
これは生物が成せる次元を超えた能力なのではないかと思う。
たぶん4次元か5次元くらい?…ちょっと分からないがそれ以上かもしれない…。
ちなみに動物も自分の感じる喜びや痛みを感じて分かち合ってくれる。
動物からしてみれば、「相手(自分)の立場からものを見れる」からだろう。

そもそも本来は、
・自分と相手が居る状態で
相手は自分をどう捉えていて、どういった気持ちや考えを巡らせているのか。
・自分と物が在る状態で
物がぞんざいに扱われて悲しいとか、手入れされて嬉しいなんて気持ちも分かるはずがない。
しかし、「注視」と「視点を変えて見る」の2つ情報を総動員すれば
相手の立場から見たときの光景や感情を予想することができる。
この予想については実際に相手が見ている光景や感情と間違いなく誤差がある。
誤差を自分の経験則から修正することで初めて
相手の視点に立つことができる。
相手の視点に立つと相手の気持ちや考えてることも芋づる式に推し量ることができる。
第一~第三段階を何度も繰り返す
ひと通り第一段階⇒第三段階まで一度見極めても、結局相手の立場から見ることに失敗したり、
誤差が大き過ぎる場合がある。
人も物事も絶え間なく変化しているため、情報は常に更新されていき、刹那で変化するだろう。
「見極める」プロセスを途中で中断すると、情報は途端に古くなり「一時的に見極めた」過去になる。
対象が物であって変化がゆっくりしたものであれば問題ないが、
人であったり事象であれば一瞬で「そういうこともあった」という過去になる。
この見極めのプロセスは自分が現在集中しているものや、好きなものに対して
人間は無意識に何度も、複合的に行うことができる。
しかも自分の経験測を交え、錯覚を修正しながら誤差を縮めることも同時進行だ。
脳のすばらしさを感じる。
いくら高性能なCPUでもAIでもこの量の情報を得ながら処理していくのは困難だろう。
まだまだ人間の方が感情の他に次元を超える能力があるため、負けていないというのが持論となる。
正確に相手の立場からあらゆる物事を見れるのであれば、相手の次の行動も容易にわかる。
夫婦の阿吽の呼吸もこの種のものだと思われる。
正確に相手の立場からものを見て、気持ちや考えを推し量るには
自身の経験を蓄積することが最も良いのではないかと思う。
物事が見えなくなったらこの方法を
「見極める」についての要素を自分なりに言語化してみた。
今の時代、真偽問わずあらゆる情報が簡単に膨大な量で飛び込んでくるため
リテラシーを持つということが非常に重要になった。
このリテラシーというのは識字能力が語源だが、現在では事象の真偽や背景を
判断する能力として用いられることが多い。

新聞、ニュース、動画コンテンツ、評論家の持論、人間関係など様々な情報があるが、
やはり1つの記事や動画、場面では物事を見るための情報があまりにも不足する。
ゆえに自分の予想と実際の真偽や背景との間に大きな誤差が生まれ、結果的に見誤るだろう。
ではどうすればいいのか。
今回紹介した3段階「注視」「視点を変えて見る」「相手の立場から見る」を
どの事象にも当てはめて、絶えず見極めるためのプロセスを複合的に循環させてみてほしい。
思想や応用すればどんな事象にも使えるはずなので、最近よく分からなくなったと
感じることがあったら試してみてほしい。
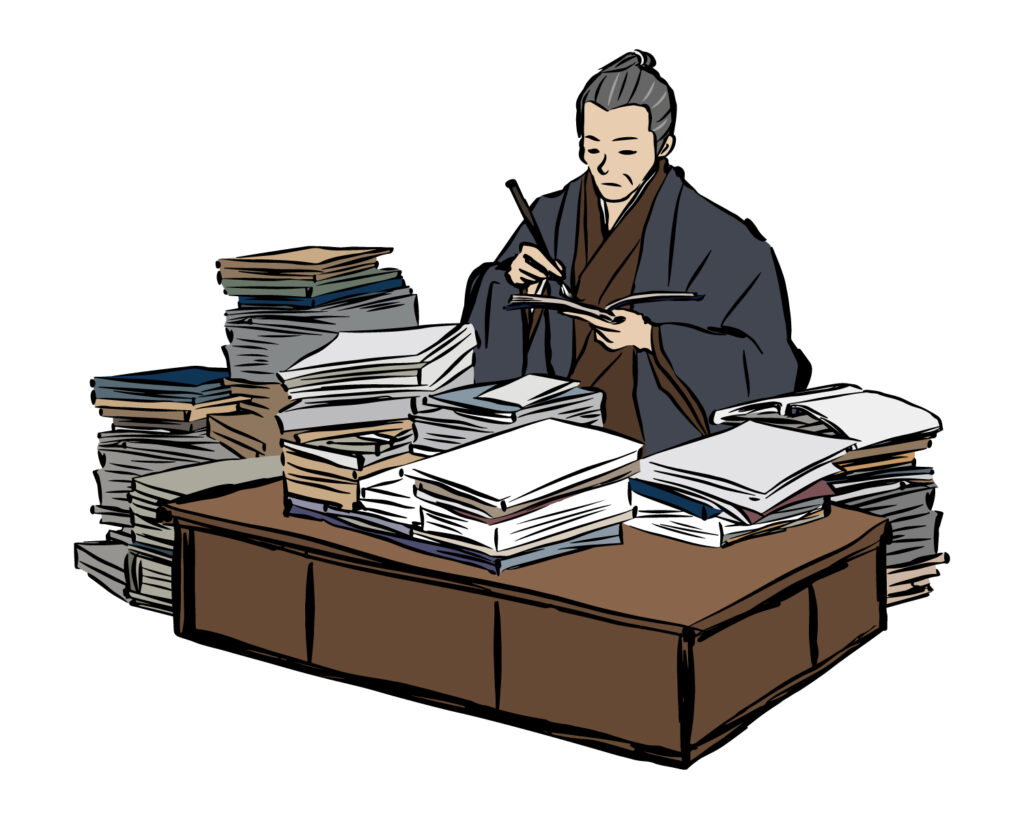
私は最近、経済についてこの3段階を当てはめて見極めを試みることが多い。
ある経済指標を見続けて(注視)、様々な記事や歴史を読み漁り(視点を変えて見る)、
最終的には証券会社や企業、国家の立場から見たときに好ましい状況と好ましくない状況を
考える(相手の立場から見る)ことで次に起こることの予想を立てたりしている。
何かに惑わされたり、妄信することはないが経験不足からか全く当たらない。もはや諦め気味である。
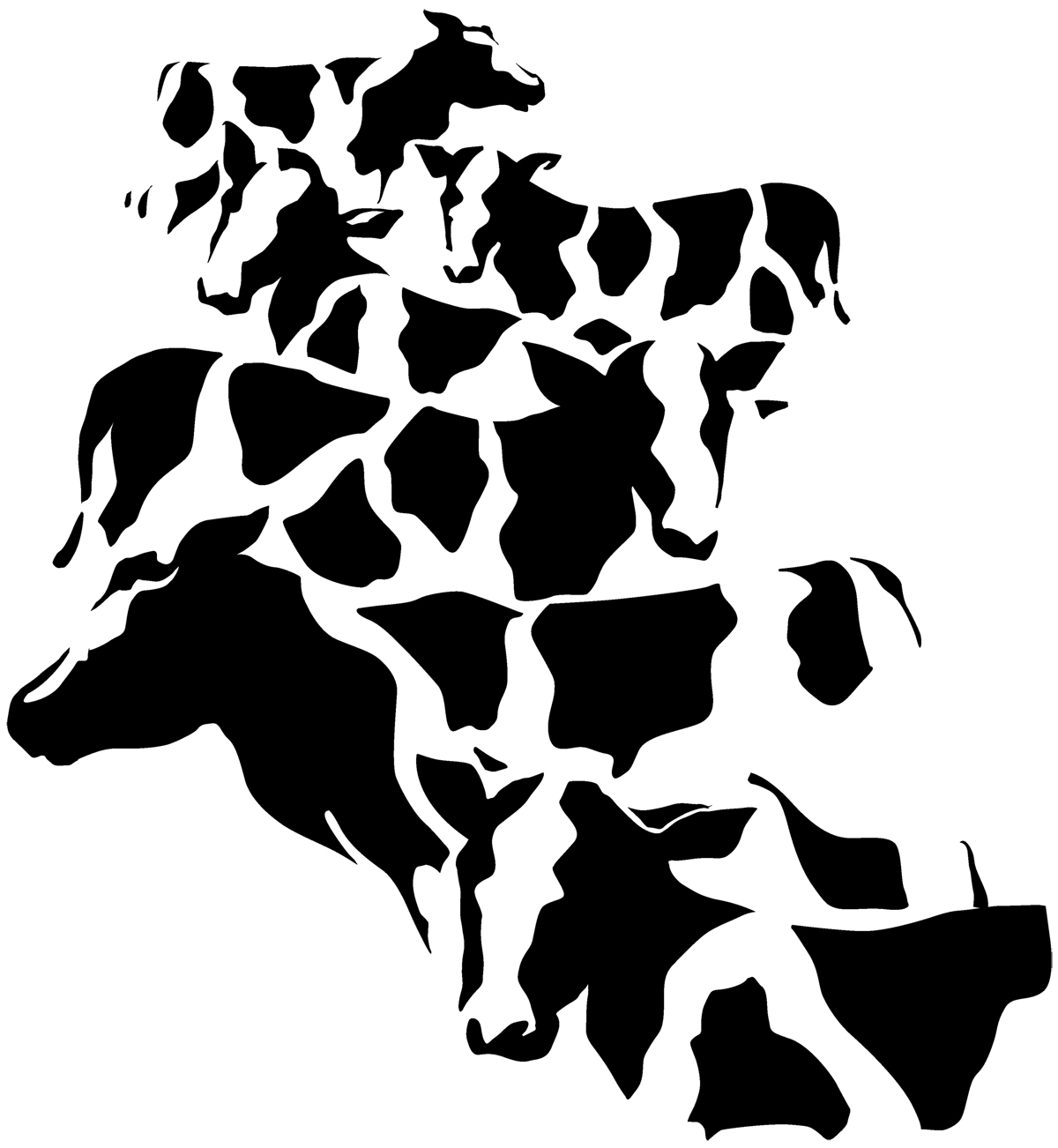


コメントを残す コメントをキャンセル