大切にした物には魂が宿るという考えがある。そして魂が宿った物は持ち主のことも大切にする。
こういった相互関係を感じたことはないだろうか。
まるで物が意思を宿して自分を助けてくれるように感じる。
なぜか昔からずっと使っている工具を使うと調子が良い、うまくことが運ぶ。
お気に入りの物を大事にしたいと思ったとき、調子が悪いとき、または壊れてしまったとき。
それは物からあなたへのメッセージかもしれない。
ぜひこの記事を読んで、長く愛用している道具・物に感謝をしてあげてほしい。
物を大切にする気持ちを思い出したり、子供への教え方として一助となれば幸いだ。
八百万の神さま
日本の独自宗教「神道」の中にある「八百万の神さま」。
昔から自然をはじめとした山の神さま、川の神さま、森の神さま。
食べ物の穀物の神さま、水の神様。
場所の土地神さま、台所の神さま、トイレの神様・・・。
以上の様々な事象や場所、物、自然に対して1人の人格(神さま)が宿ると考えて
敬うことがこの「八百万の神さま」。

実は「神道」という宗教的な形ではなく、何気ない日常的な形で我々日本人には
この思想が伝えられ教えられてきた。
神道だったのか、と驚く人も多いと思うが私もこの記事を書くまで
知らなかった。宗教はともかく物を大切にするうえでとても良い思想なので
受け継ぎ・語り継いでいきたい。

物を大切にする日本の教え
日本では幼い頃から物を大事に扱うよう親から教わる。
ところが、「大事にしなさい」とか「高かったんだぞ」と損得で教わるよりも、
全く別のニュアンスで教えられなかっただろうか。
- 物を乱雑に使ったとき
「そんなことしたら○○(物の名称)が可哀そうでしょ」
「○○が痛いって言ってるよ」 - 無くしたと思っていた物が出てきたとき
「大事にしてたから帰って来たんだよ」
「持ち主のこと好きだから戻ってきたんだよ」 - いつも使っている物が壊れたとき
「何かの身代わりになってくれたんだよきっと」
「役目を終えたから休ませてあげよう。ありがとって言うんだよ」
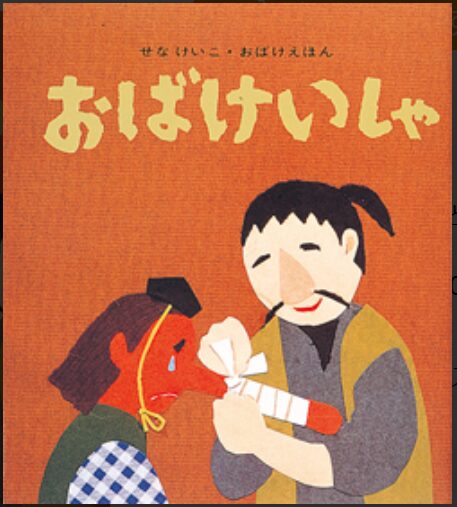
【著者】せな けいこ
【出版社】童心社
ちなみに、
私が子供の頃によく親が読み聞かせてくれた絵本。
この本で登場するおばけには、
人間にぞんざいに扱われて壊れた物のおばけも
登場する。
あたたかいお話と優しい絵で寝る前にも最適だ。
子供へ物を大切にする気持ちを
育むことができるので是非おすすめしたい。
物一つに1人の人格があって、それを尊重するように教えられる。
ちなみに映画「千と千尋の神隠し」でも、物や自然に宿った八百万の神さまを
湯屋に迎える様子が描かれている。
よって子供の頃から何気なく神道の教えを引き継いでいるため、すぐに物に人格という
不可思議な状況を飲み込めることだろう。
日本人の物を大切にする気持ちはきっとここから来ている。
昔からある「物が壊れた」ときの話
ものが壊れた時についての「言い伝え」は誰しも聞いたことがあるはず。
下駄の鼻緒が切れたときは縁起が良くない。
鏡が割れたときは不幸になる。
陶器が割れたときは家族や身の回りの争い事を予兆。
逆に靴や服などが壊れたりした際には新しい物を纏うようになることから
自身に変化の兆しとして縁起が良いという考え方も伝わる。
車をぶつけることも、当たるに掛けて宝くじが当たるというゲン担ぎも存在する。

普段から自身が身に着けている物や、仕事道具、愛用している物。
これらが壊れた時には非常に落ち込むもの。
しかしただ単に「壊れた」ということだけにとどまらないということを日頃から
意識しておくと、その後に続く「変化」に備えることができるはずだ。
そして後々気付く、お気に入りの物が壊れたあの時。
もしかして救われていた、或いは身代わりになってくれたのではないか、と。
物が起こす行動
よく身に着けているものや愛用しているものによく起こること。
それは使おうと思った時に見つからない。
または予期しないタイミングでの故障や不調だ。
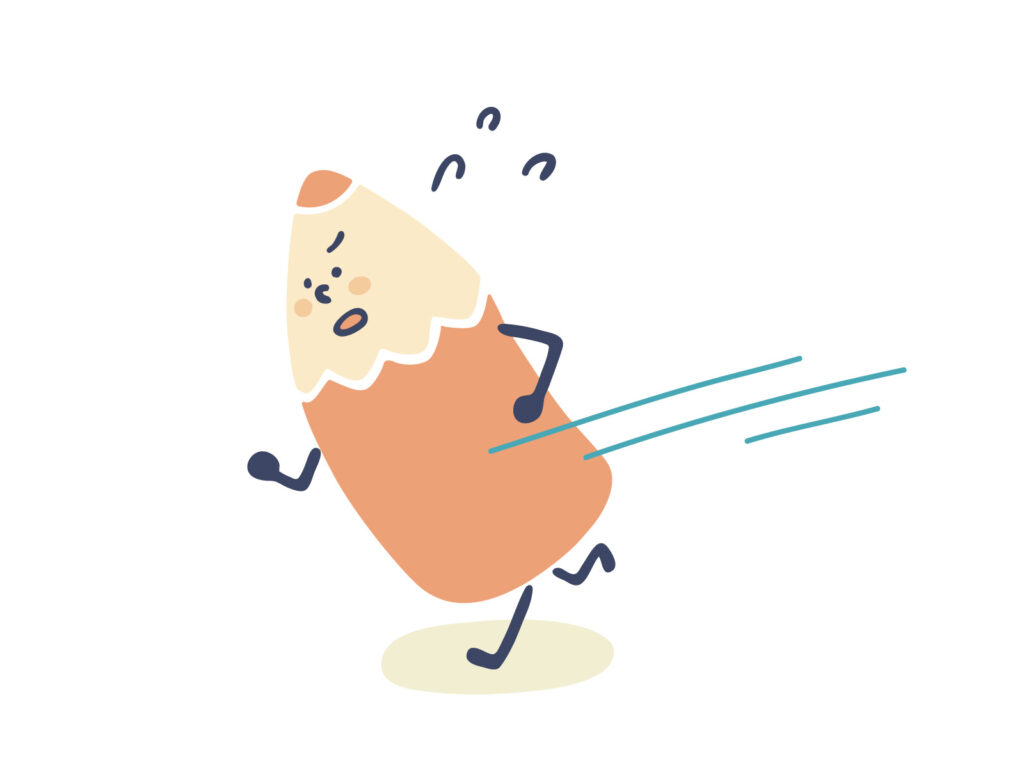
これらの現象は大事にしているものに限って多い。
事態が発生すると使用者は非常にショックを受ける。
または作業中や何かをしている途中でのタイミングなら
それらを中断することになる。
つまりここで大小問わず「変化」が発生する。
この「変化」は道具が何かしらのメッセージを使用者へ発しているのだと感じる。
きっと大事にされた道具たちはこの時、このように考えているのかもしれない。
- 今日は調子が良くないから運転するのは避けた方が良い。
- 疲労が溜まっているから一時作業を中断して休むと良い。
- 大事なことを忘れている、今はこうしている場合ではない。
事例としては、
用事のため出かけようとする⇒車の鍵が見つからない⇒諦めて電車にする。
納期に追われて仕事が続く⇒突然工具が不調に⇒仕事を切り上げて手入れする。
大切な人から貰った物が壊れる⇒大切な人を思い出す⇒連絡して会う。
人格的な言い方をすれば、これらの事態は物が持ち主へ何かを伝えたいのではないか。
買うときは愛着が湧くかどうか
物を厳選せずに沢山持ってしまうと、量が多すぎる故に大切にできない物が出てくる。
埃を被らせたまま放置していては八百万の神さまとして敬うどころではない。
※その点でいうとミニマリストの必要最低限しか持たない意識は、
物の総量の少なさから、持っている分を余すことなく大切にすることができる。

風水的にも物がたくさんあるという状況は良くないとのこと。
ミニマリストまでとはいかないが、ある程度生活に必要な分と自分が気に入ったものだけに
して総量を絞る、減らす意識は重要だ。
生活品だとしても、末永く使う物は愛着のあるものが良い。
だから物を買うときや貰うときには愛着が湧くかどうかを直感で感じ取り、
厳選する必要がある。

ここでも物の人格的性格を考慮していうと、物との出会いも一期一会なのだと強く感じる。
実はお互いに引かれあって運命的な出会いを遂げた物もある。
こういうのは直感でビシビシ感じるだろうし
実際使ったり、身に着けていると不可思議なほど良い境遇にあったりする。
物に対して運命的な出会い、数奇な事象に遭遇した人も多いのではないだろうか。
愛用している物に感謝とお手入れを
時には物が自分の身代わりを果たしてくれることもある。
文頭に説明した「八百万の神さま」神道とは違う考え方からくるものだ。
特に大事にしていたものは、明らかに身代わりを務めてくれた…という場面も。
突然のアクシデントで自身の身に降りかかってきた災いを
愛用している仕事道具が身を守ってくれた。
現場仕事を長くやってきた人にはそんな経験もあるはず。
お気に入りで長く愛用している物には、目に見えず感じ取れない場所で
多々助けられているのではないか。
そう思うと益々愛着が増え、物に対して感謝できる。

愛用してきた物手入れできてますか?日常の忙しさで埃が被ってないですか?
お手入れしてあげたら物はきっと喜びます。
そしてまた知らず知らずのうちに、持ち主へ恩返しをしてくれるに違いありません。
壊れたり、無くなったりするのは、恩返しの結果かもしれませんね。
お気に入りの物や愛用品が起こした数奇な事柄や、思い、感想などいただけると幸いです。



コメントを残す コメントをキャンセル